2025年6月、日本の造船業界にとって歴史的な再編が発表されました。
国内最大の造船会社である今治造船が、業界2位のジャパンマリンユナイテッド(JMU)を子会社化するとのことです
このニュースはマイナー紙に限らず多くのメディアでも大きく取り上げられています。
この動きは単なるM&Aではなく、日本の造船産業の競争力を取り戻すための戦略的な再編とも言えます。
少なからず造船業に関わりのある私が会社で一人騒いでいましたが、若い子から見たらただの痛いやつに写っていたことでしょう。
そんな冷たい視線を軽やかにスルーし、今回の衝撃ニュースをおじさんなりに簡単にまとめてみました。
 | 改訂版 本当の自由を手に入れる お金の大学 [ 両@リベ大学長 ] 価格:1650円 |
今治造船とJMUってどんな会社なの?
まずは両社についてザックリとおさらいしてみましょう!
今治造船:世界有数の大型船メーカー
今治造船は、愛媛県今治市を本拠とする日本最大の造船会社です。
世界的にも有数の建造量を誇り、特にばら積み貨物船や自動車運搬船といった大量輸送向けの大型船を得意としています。
長年の実績と高い技術力により、国内外の多くの船主から安定した受注を確保しています。
【愛媛県が生んだ日本一の造船会社】今治造船株式会社にスポットを当ててみた
JMU(ジャパンマリンユナイテッド):高付加価値船に強み
JMUは2013年にIHI・JFEなど複数の大手造船企業の統合によって誕生しました。
横浜や呉、舞鶴など日本を代表する歴史ある造船所を持ち、LNG船やタンカー、護衛艦といった高性能・高付加価値の船を建造しています。
軍需・エネルギー輸送分野に強みがあり、日本の高度な技術を支える重要な造船企業です。
【複雑な家系?!大手重工企業が合体して誕生した造船企業】ジャパン マリンユナイテッド株式会社にスポットを当ててみた
なぜ再編が必要なのか?
この再編の最大の目的は、国際的な競争で生き残るための体制づくりだとされています。
中国や韓国の造船企業と戦うには国内企業同士で競っている場合ではありません。
国内企業同士で手を取り合い、造船大国日本を取り戻そう!みたいな感じですかね(´ε` )
【再編の背景】
- 中国造船業の台頭
中国政府が主導する産業再編により、巨大造船グループが誕生し業界を牽引。
圧倒的な生産力と低価格で世界シェアを拡大中! - 韓国の高性能船戦略
韓国は早くからLNG船や自動運航技術に注力し、先進的な船で高収益を確保。
対中姿勢のアメリカとも良好な関係を構築し、より強い産業へと成長中! - 日本は技術力は高いが、企業が分散し非効率
各社が独立して競い合う構図のままでは調達コストや開発スピードで不利。
島国という環境で、限られたリソースをどう活用するかが重要な局面に。
※2024年の新造船シェア割合はザックリこんな感じ
中国:70% 韓国:15% 日本:10% その他:5%
このような状況を受け、今治造船とJMUは「競争」から「協業」へと舵を切り、日本造船業界の生き残りと再成長をかけた新たな体制を築こうとしているわけなのです。
トップ2が手を取り合う今、その他中堅造船所も様々な策を講じて生き残る術を模索していくと予想されます。
今回の子会社化で何が変わる?
今回の報道前後でJMUの持株比率がどう変化したのでしょうか?
報道前(2025年6月26日前)
- 今治造船:30%
- JFEホールディングス:35%
- IHI:35%
報道後(2025年6月26日発表以降)
- 今治造船:60% (+30%) ※筆頭株主
- JFEホールディングス:20% (-15%)
- IHI:20% (-15%)
筆頭株主になると?
持分比率が30%から60%に増えることで、端的に言えば「実質的な経営権を握る」ことになります。
【報道前】30%保有 → 重要な株主
- 経営に一定の発言力はあるが、他の大株主(たとえば35%を持つJFEやIHI)と協調しないと物事が思うように決まらない。
- 取締役の選任や経営方針に関しては単独で決定できない。
- “共同経営”に近い状態。
【報道後】60%保有 → 親会社(筆頭株主)
- 議決権の過半数(50%超)を持つため、会社の重要事項を単独で決定できるようになる。
- 例:取締役の選任・解任、定款変更、合併・解散など。
- JMUは今治造船の子会社となり、連結決算上も今治造船の業績に含まれる。
- グループとしての資源(人・モノ・金)を柔軟に配置でき、本格的な経営統合が可能になる。
| 項目 | 30%時(旧体制) | 60%時(新体制) |
|---|---|---|
| 経営判断 | 他株主との調整が必要 | 今造が主導で決定可能 |
| 投資戦略 | 協議ベース | 単独で迅速に判断 |
| 組織再編 | 制約が多い | 再編や人員再配置が柔軟に |
| 企業グループ | 関連会社 | 完全な子会社として一体運営 |
まとめ
60%の株式を保有するということは「株主のひとり」から「支配する親会社」になることを意味します。
今治造船はこのステップを踏むことで、JMUとの実質的な経営統合を進め、“ひとつの造船グループ”として世界と戦える体制を作ろうとしているといえます。
持株比率の変化によって期待される効果
- 経営判断の迅速化
今造主導で方針が定まりやすくなり、意思決定や投資判断がスピーディーに行われることが期待されます。JMUは良くも悪くも大企業の文化(稟議書のスタンプラリー等)がありました。すぐに変わることは難しいかもしれませんが、徐々に改善されると思われます。 - 製販機能の連携強化
すでにこの2社はNSY(日本シップヤード)で設計と営業機能において協力体制を整備していました。
今回のグループ化によって、鋼材などの原材料調達や製造拠点の統合によるスケールメリットの追求が本格化するとの話が聞こえてきています。ITインフラ等の基幹システムも段階的に統合されることも考えられます。まさに「一枚岩」といった感じになるのでしょうか。
全社的な機能統合によって「より強いグループ」へと進化する狙いがあると言えそうです。
地域や働く人たちへの影響は?
今治造船とJMUはいずれも全国各地に造船所を抱え、地域の主要雇用主としての役割を果たしています。
- 地域経済への安定効果
グループ再編による事業の継続性が確保されることで、各地の雇用や地域経済の安定や貢献につながります。JMU舞鶴が新造船を撤退(縮小)するときは、それはもう大変なことだったらしいですから・・・笑 - 若手人材の採用と育成に弾み
魅力ある成長企業としての姿勢が明確になり、若い技術者やエンジニア志望者の就職先として注目される可能性があります。人材不足の昨今では、より重要な要素となります。 - 伝統技術と最先端技術の融合
地域に根付いた熟練工の技と新しい開発技術が融合することで、日本のものづくりの深みが増していきます。さまざまな分野や工程でAI技術が取り入れられるようになってきましたが、まだまだベテランの技術なくしては船を作ることはできません。
「人づくり」と「地域づくり」につながる重要な一歩でもあると言えます。
 | 改訂版 本当の自由を手に入れる お金の大学 [ 両@リベ大学長 ] 価格:1650円 |
【まとめ】再編は日本造船業の再出発の合図
今回の今治造船によるJMU子会社化は、単なるM&Aではなく「業界全体を支える変革」だと言えます。世界の造船勢力図が大きく変わりつつある中、今こそ連携と効率化によって新たな競争力を手にする必要があります。今回の再編はその第一歩となります。
今治造船グループが誕生することで、日本の新造船建造量のおよそ半分を担う巨大造船企業グループが誕生することになりました。
しかし、中国や韓国からすればまだまだ脅威にはならないのかもしれません。
【2024年時点での建造量ランキング】
| 順位 | 造船会社(国) | 年間建造量(GT) |
|---|---|---|
| 1位 | 中国船舶集団(CSSC, 中国) | 3,148万GT |
| 2位 | HD現代重工業(韓国) | 614万GT |
| 3位 | サムスン重工業(韓国) | 561万GT |
| 4位 | 今治造船+JMU(日本) | 500万GT |
とはいえ、日本政府も含め変わろうとする姿勢は強く現れ始めました。
これからの日本の造船業が、どんな新しい船を生み出し、世界でどんな活躍を見せてくれるのか・・・
この歴史的な再編は、未来のものづくりや地域社会、若者の進路や夢にもつながっていくことは間違いないでしょう!
造船大国日本への道はまだまだ始まったばかりです。
今後も日本の造船業界の進化に注目していきたいと思います。
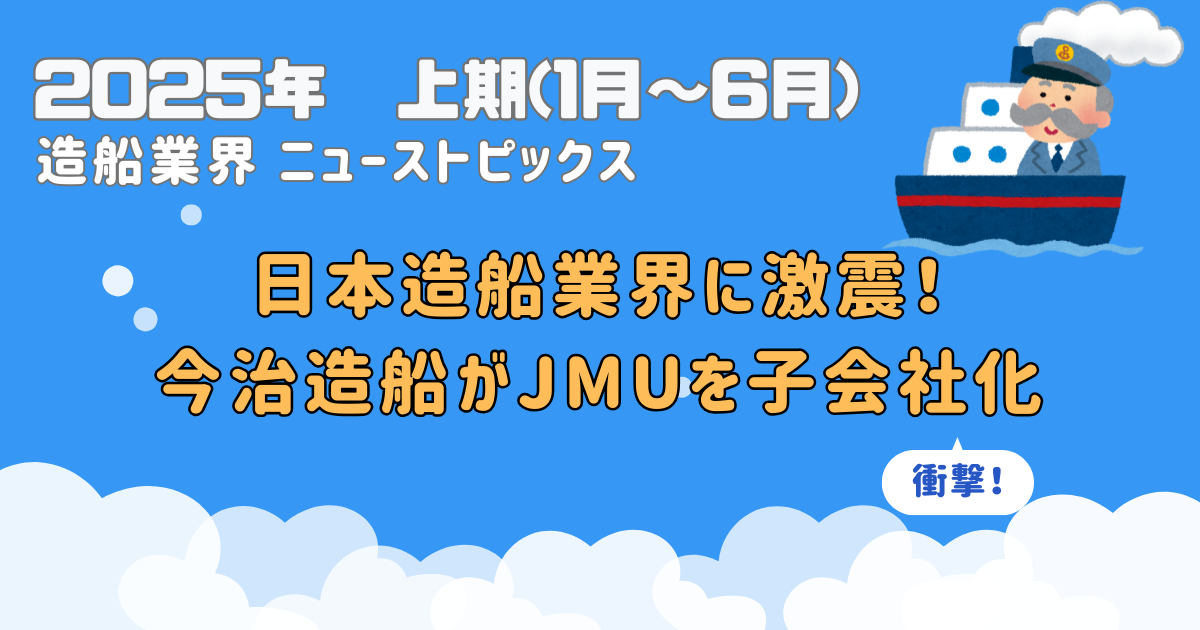

コメント