2024年の造船業界ふりかえり
2024年は日本の主要造船所にとって良い年になったと言えるのではないでしょうか?
2025年を迎え、2024年造船業界の簡単な振り返りと2025年の展望をつらつらっと書いてみます。
まずは一番わかり易い数字(業績と株価)でどんな感じだったのかをチェック!
25年1月時点では、上場企業(内海造船、名村造船所)の2025年3月期業績の上期までの数値が開示されています。
【2025年3月期 中間決算】
内海造船 売上高:22,787百万(前年比△13.5%) 経常利益:377百万(前年比△86.0%)
名村造船所 売上高:78,287百万(前年比+29.1%) 経常利益:14,583百万(前年比+88.2%)
2023年度比では明暗が別れたように見えますが、黒字という意味では好調が継続されていると解釈して良いと思っています。
まさに造船バブル相場とも言える2023年末~2024年夏頃と比べ、現在は6〜7割程度の株価になっていますが、コロナ前と比べると断然高値圏です。
日本一の造船企業である今治造船やJMUの業績も期待できそうです。
ちなみに、JMUの上期経常利益は昨年度比で5倍弱と高水準でした。
日本の造船所が得意とするバルカーの価格は昨年末から横ばいの状況が続いています。
資機材価格や人件費の高止まりに加え、主要造船所が3年以上にわたる十分な手持ち工事量を確保したことで、安値受注はせずに高利益が見込める案件を選別して取り組む余裕が出てきています。
一方、海運市況は2024年秋以降に軟化し始め、造船会社と船主の新造船希望価格差が拡大しており、当面は新造船の成約件数が落ち着く可能性がありそうです。
 | 改訂版 本当の自由を手に入れる お金の大学 [ 両@リベ大学長 ] 価格:1650円 |
国内造船所の現状と戦略
豊富な手持ち工事量
2024年、国内主要造船所は2028年前半までの船台をほぼ埋め、2025年は2028年後半~2029年納期の受注活動を進める見通しです。
29年度納期分の契約が既に始まっているとの情報もあります。
この状況により、新規成約が少なくても事業継続への影響は限定的となるため、高利益率案件に絞った受注活動を行う余裕が造船所に生まれてきています。
コスト増の影響
- 鋼材価格
2024年は鋼材価格が高止まりし、造船所にとって価格を引き下げる余地はほとんどありませんでした。製鉄企業は高付加価値鋼材に注力すると表明していることから、鋼材価格の下落に伴うコストダウンを望むのは難しい時代になったと言えそうです。 - 舶用機器や資器材、人件費
各種資器材に始まり船舶に搭載する舶用機器のコスト上昇が続き、労働力不足に伴う人件費の高騰も業績に大きな影響を与えています。採用する計器やシステムに省人化や自動化の取り入れが急務であり、開発コストや設計見直しなどの負担が造船所に大きくのしかかってくる可能性もあります。
新造船価の動向と市場背景
主要船型の価格推移
- ケープサイズ
2024年12月時点で7000万ドル台後半で横ばい。上昇基調が一服した様子。 - カムサマックス
2024年6月には4300万ドルと最高値付近の成約を記録。船価は横ばい。 - ハンディサイズ
2024年6月には3400万ドル程度まで上昇。年末ごろから若干の下落傾向。
新燃料船のコスト加算
環境規制対応として需要が高まる新燃料船は従来型に比べてコストがさらに上乗せされ、価格水準が一段と高くなっています。
今後のトレンド読み合戦になっていて、造船所ごとに新燃料船の戦略が見え始めてきています。
会社の存続に直結するほどのことではないかもしれませんが、方向性を見誤った造船所は新燃料船市場では出遅れることになります。これからの動きからは、ますます目が話せません!
海運市況の影響と船主の心理
2024年の市況変動
ドライバルク市況は2024年の10~12月に軟化傾向へ。米中貿易摩擦による鉄鋼原料輸送への影響懸念が高まり、船主の発注意欲が低下している様子。
用船料市況とのギャップ
新造船価は依然として高水準にある一方、用船料市況の雲行きが怪しくなりはじめ、船主の採算見通しが厳しくなっています。
用船契約を結ばずに船舶を発注する場合、心理的な不安がさらに増幅して投資意欲の減退につながる可能性がありそうです。
今後の見通しと課題
成約の鈍化予測
2025年のドライバルク市場は、成約件数が2024年を下回る見込みです。
また、28年後半~29年納期の船舶は先物すぎるリスクを懸念した船主(用船者)の関心が薄れる懸念も指摘されています。
造船所の営業戦略(方針)
手持ち工事量が豊富なため、造船所は価格を維持しながら長期的な収益確保を優先する姿勢です。一方で、資材コストや人件費の負担が続く中、競争力を維持するための効率化や新技術の導入が重要課題となります。
まとめ
2025年、日本の造船業界は手持ち工事量の豊富さに支えられた心理的余裕を背景に、利益率を重視した受注戦略を進めることが予想されます。さまざまな面でのコスト上昇や市場変動の影響懸念は引き続き残ります。これにより、新造船の成約件数が前年を下回る可能性が高いものの、環境対応船の需要は強く、一定の新造船需要は継続されるものと想定されます。国としても日本の造船業を強くする意思を明確にし始め、各造船所の国際競争力を強化すべく補助金事業を進めています。すでに補助金の採択結果は公開されていますので、その話は別途まとめるとしますが、今後も一定期間は継続されるであろう造船業界の良い流れを楽しみに2025年を過ごしたいと思います。
※様々なニュースや造船所の中の人のコメントを参考に個人の解釈で記事を作成しています。細かい数値やニュアンスに間違いがあるかもしれませんのでご了承ください。
 | 改訂版 本当の自由を手に入れる お金の大学 [ 両@リベ大学長 ] 価格:1650円 |
補足(2025年1月17日時点)
| 社名 | コード | 株価 | 時価総額 | PER | ROE | PBR | 配当金 | 配当利回り |
| 内海造船 | 7018 | 4,265 | 72億 | 10.3倍 | 22.7% | 0.7倍 | 40円 | 0.9% |
| 名村造船所 | 7014 | 1,813 | 1,258億 | 5.7倍 | 21.4% | 1.3倍 | 35円 | 1.9% |


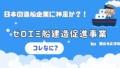
コメント