今年も早いもので6月中旬になりました。もう半分を終えてしまうのですね・・・・
時間の経過する速度が年々加速しているように思え、おじさん自身の衰えを痛感します。
そんな話はさておき、今年上期の日本造船業界はどんなんでしたかね?
おじさんが特に気になったトッピックスを複数回に分けて書いていこうと思います。
おじさん的にはここ数年の活況が継続されている反面、前途多難な状況がますます悪化しているように思えてなりません。人手不足に中韓勢の衰え知らずな勢い・・・・
日本造船企業の復権には、各社が手を取り合い同じ方向を向いて世界と戦う覚悟をするしかないと思っています。覚悟するとは、変なプライドを捨てるということです。ネームバリューとか歴史とか、そんなもので飯を食える時代は終わったと理解し、今あるべき形を目指してほしいです。
これさえ見ておけば、日本造船業界の大枠は理解できる!
とまでは言いませんが、参考までにどうぞ〜♪
※おじさんは中の人ではありませんので、ここにしかないようなマル秘情報は全くでてきませんよwww
 | 改訂版 本当の自由を手に入れる お金の大学 [ 両@リベ大学長 ] 価格:1650円 |
2025年 上期ニューストピックス 3選
受注残が約3.7年分に拡大!建造能力不足が課題
各造船企業(特に中大手)の新造船受注が好調を継続し、手持ち工事量がさらに拡大しました。
2025年4月末時点での受注残は621隻・2951万総トン(1360万CGT)に達しています。
これは24年の輸出船竣工量に基づくと、約3.7年分の工事量に相当します。
世界的な環境規制強化や船舶の世代交代需要が背景にあり、用船料と新造船価格差がネックになっているとのニュースもありますが、今後も新造船需要は続く見通しとされています。
一方、造船所の建造能力や人材リソース不足が深刻化しており、納期の長期化やコスト上昇の懸念も指摘されています。
各企業は設備投資や省人化技術の導入を急ぐとともに、受注の選別や高効率な生産が求められる局面となっています。
おじさんの懸念
昨今は各種補助金の活用による設備投資のニュースを目にする機会が増えました。
日本政府が造船業界に予算を割り当ててくれているのは良いことですが、長い目で見ると少し怖いです。補助金は言ってみればドーピングです。ドーピングありきでしか設備投資できない企業体質(資金管理)になったら、遅かれ早かれ衰退します。
様々な設備の供給メーカも限られており、補助金ありきな状況を把握しているがゆえに、かなり高額な金額を提示してきているとも聞いています。
補助金がなくなった未来には、あるべき金額で金額提示することができなくなった設備メーカと、自己資金では設備投資することができない造船企業が溢れている。そうならないことを祈るばかりです。
日米が造船分野での協力を強化へ
日米間の関税交渉において造船分野での協力が一つの大きなテーマとなりました。
世界の造船市場において中国が圧倒的なシェアを持つ中、アメリカは自国造船業の復活を掲げました。また、アメリカは日本の高い技術力や修繕能力に期待を寄せています。
日本は砕氷船など特殊船舶で強みを持つことから、アメリカの経済安全保障政策とも合致。
日本政府は日米協力を軸とした造船業再生戦略を打ち出し、6月には「骨太の方針」に関連施策を盛り込む見込みです。
具体的には、日米共同でのアンモニア船や自動車運搬船の開発、米国内修繕ドックの整備支援、重要部品の安定供給体制の構築などが挙げられます。
さらには、日米造船業再生ファンドの設立も検討されており、経済安全保障の観点から日本の造船業への支援が強化されると思われます。
アメリカでは2025年の秋以降、中国関連船舶への入港規制や課税強化が予定されており、日本企業にとっては米国市場でのビジネスチャンスが拡大するだろうと期待感が高まっています。
おじさんの懸念
アメリカのみならず韓国とも協力して中国一強の造船業を取り戻すかのようなことが書かれていますが、本当にそうなるでしょうか?
政治批判をするつもりはないですが、今の日本の政治家が上手いこと事を運ぶとは到底思えません。技術協力と言いながら、ただでさえ足りていない人的リソースや高い技術力を安売りしてしまうのではないかと・・・・
政治的にはプラスかもしれませんが、結果的に日本造船業界的には大きな負荷(足かせ?)になってしまっては本末転倒。
中国一強の現状に、そよ風を吹かせた程度に留まり、気づいたら日本の造船企業が疲弊して崩壊寸前です・・・・とならないよう祈ります。
フェリー新造船ラッシュ!環境対応と大量代替期が重なる恐怖・・・
2025年は国内フェリー市場で新造船の発注が相次ぐ「新造船ラッシュ」の年となっている模様。
この背景には、2028年前後に多くの国内フェリーが船齢25~30年の代替期を迎える見込みであることや、コロナ禍で更新が遅れていた反動、国際海事機関(IMO)の規制強化があるとされています。
旅客定員を減らし貨物輸送ニーズに応える設計や、デジタル運航管理システムの導入も進んでいます。
一方で、造船所の設計リソースや人材不足が課題となっており、今後の需給バランスや納期調整が業界の重要テーマとなっています。
そもそもフェリーを得意としている造船会社は多くありません。また、同型船の連続建造案件になることもないため、高利益を確保することも難しいです。
客船は内装にもかなりの工数と手間がかかり、一般的な商船よりも大変(めんどくさい)と聞きます。
今後は、少しでも利益を稼げる商船の連続建造を手掛けるのか、過去経緯を踏まえて単発のフェリー代替案件に対応するのか?フェリーを多く手掛けてきた企業は選択を迫られることでしょう。
 | 改訂版 本当の自由を手に入れる お金の大学 [ 両@リベ大学長 ] 価格:1650円 |
まとめ
2025年上期の日本造船業界は、近年の活況な状況が継続している様子がうかがえ、日本政府の造船業支援が進み始めるという大きなポイントになる時期でした。
世界的な環境規制の強化や船舶の世代交代需要が追い風となり受注残は約3.7年分に拡大。
造船所の建造能力(人材)不足がより明確になり、いよいよ見過ごせない状況になってきました。
これは、国内拠点を維持し地域経済や雇用を支える日本造船業にとって大きな転換点になると言えそうです。
また、韓国や中国の国家的支援による価格競争は依然として厳しく、日本の世界シェアがギリギリ二桁台という厳しい現実を突きつけられています。
日本造船企業の今後の成長には、ゼロエミッション船など環境対応船の建造体制強化や、AI・自動化技術の導入による生産性向上が不可欠です。さらには、熟練技術者の高齢化や若手人材の不足といった構造課題も深刻であり、人材育成や技術伝承が急務です。政府や業界は、スマートファクトリー化や国際協業の推進を通じて競争力強化を目指すようなので期待したいところです。
今後は、環境対応・デジタル化・人材確保を軸に、持続可能で国際競争力の高い産業への進化が求められます。世界的な需要増加の波を捉え、再び「造船大国日本」としての地位を確立できるかが、日本の造船業界にとっての大きなポイントになりそうです。
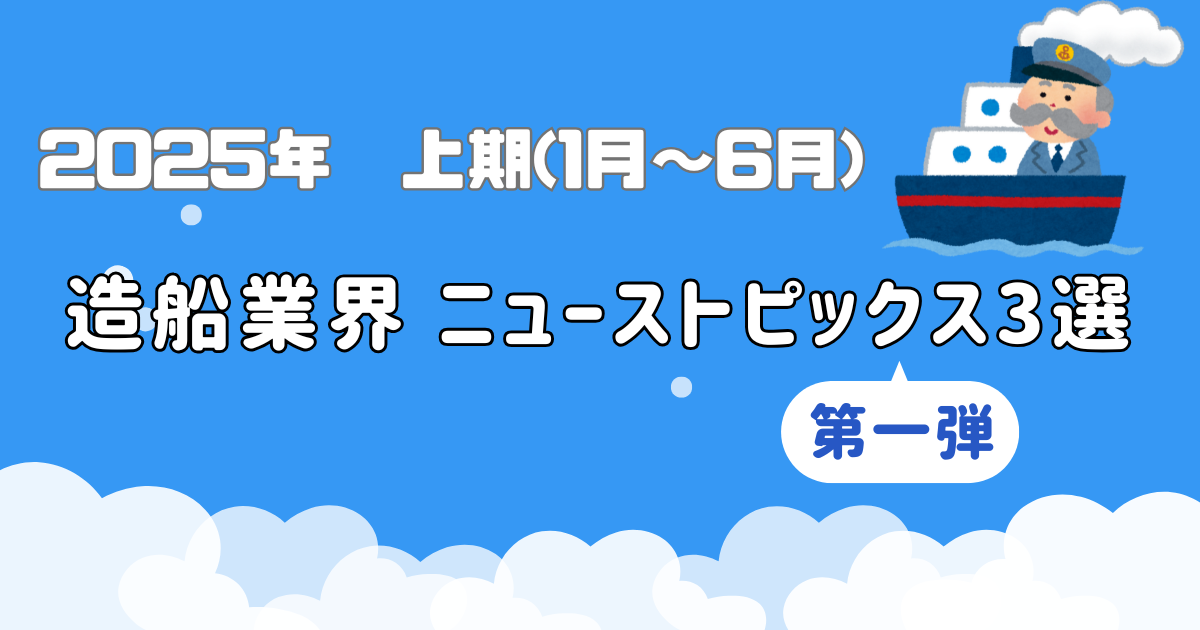
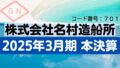
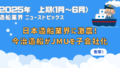
コメント